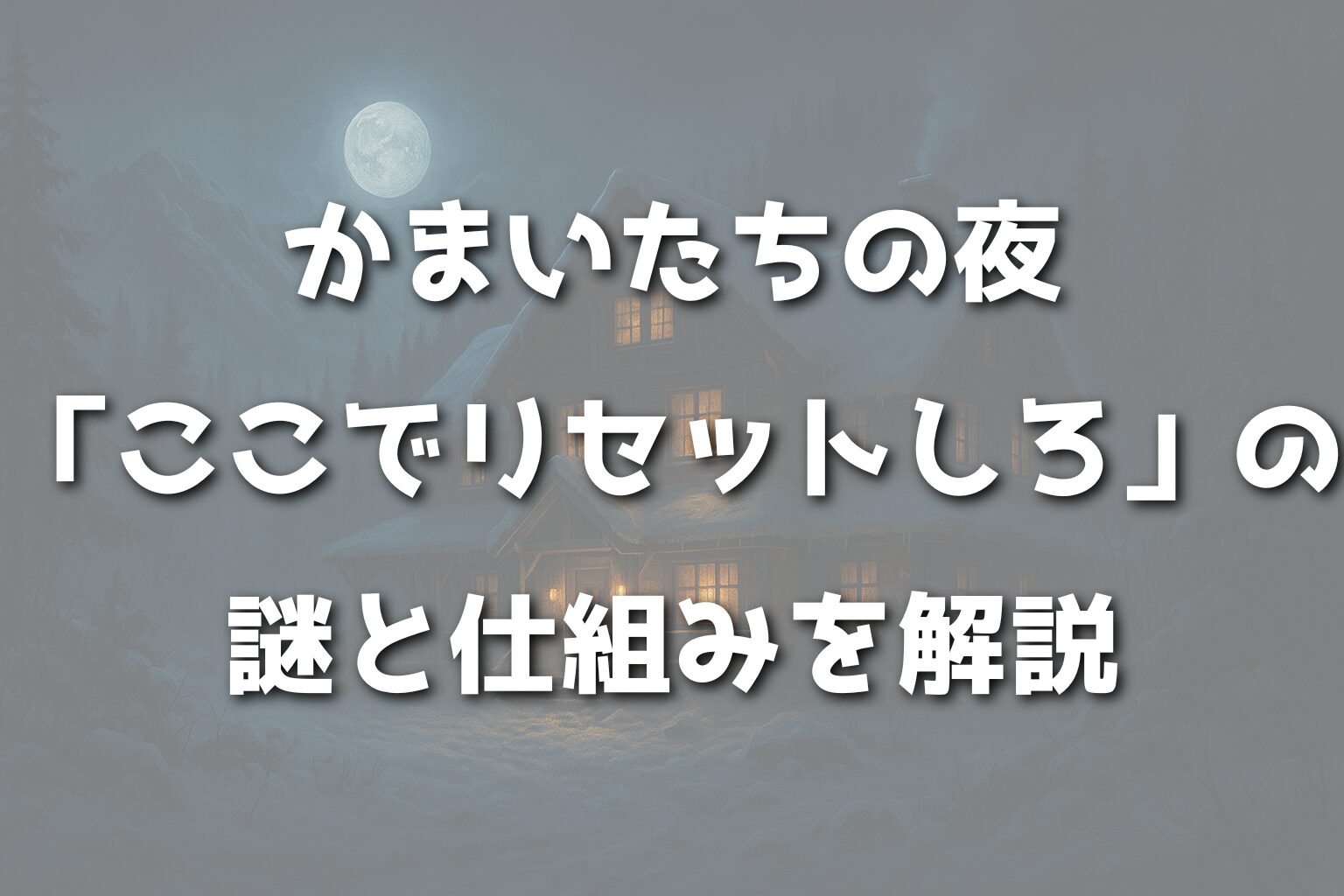
nerdnooks・イメージ
あなたは伝説のサウンドノベル「かまいたちの夜」に隠された、あまりにも有名な不思議なメッセージ「ここでリセットしろ」の噂を聞いたことがありますか?このゲームをプレイした多くの人が、その不気味な体験談や隠された謎について語り合ってきました。特に、特定の条件で表示されるというこのメッセージは、多くのプレイヤーに強烈な印象と好奇心を植え付けた要素の一つです。
1994年に発売されたチュンソフトのサウンドノベルは、雪山のペンションを舞台にした猟奇殺人事件を描いた作品ですが、そこに隠された「ここでリセットしろ」というメッセージは単なるゲームオーバー表示ではなく、プレイヤーの常識を覆す独特の仕掛けでした。この記事では、暗号の正体から、噂される電話番号の真相、さらに隠しシナリオの内容まで、要点を整理して解説していきます。
- 「ここでリセットしろ」というメッセージが出現する条件とその真相
- リセットボタンを押した時に表示される「チュンソフ党の陰謀編」の内容
- プラットフォームごとに異なる隠しメッセージの仕組み
- 都市伝説として語り継がれる「謎の電話番号」の真実
関連記事:
かまいたちの夜でリセットしろという謎めいた指示の真相
スーパーファミコン『かまいたちの夜』より、本文中の縦読み。
「たすけてくれ!」
「ここで理せっとしろ」指示通りリセットするとそこには衝撃の告発が……
通常文字通りゲームをリセットするはずのボタンを押しても話が続く演出には驚いた😲#それは反則だと思ったゲームのシーン pic.twitter.com/NEheAIm6Ul
— アジャラカモクレン (@ajarakamokuren) April 14, 2024
- 暗号編の宝探しシーンで見つかる縦読み
- 「ここで理せっとしろ」の正確な意味
- リセットボタンを押すとどうなるのか
- チュンソフ党の陰謀編への入口
- 移植版での違い(セレクトボタン等)
暗号編の宝探しシーンで見つかる縦読み
「ここでリセットしろ」のメッセージに辿り着くには、まず本編(ミステリー編)をクリアした上で、追加シナリオの「暗号編」をプレイする必要があります。この暗号編は、ゲーム内のセーブデータ(しおり)が「ピンク色」に変化した状態で解放されるシナリオの一つです。ピンクのしおりは、バージョンによって条件が異なり、例えばPS/GBA版では青のエンディングを21種類見ることで出現します(SFC版では異なる条件があります)。
暗号編の終盤にある宝探しのシーンでは、香山というキャラクターが複数行にわたる謎めいたセリフを話します。ここで重要なのは、各行の特定の文字(代表的には左から3文字目ですが、機種によって差があります)を縦に読んでいくという「縦読み」の手法です。縦読みすると、スーパーファミコン版では「ここで理せっとしろ」という文字列が浮かび上がってきます。
このメッセージはただの演出ではなく、プレイヤーに対する直接の指示でした。実際にこの画面が表示されている間にリセットボタンを押すことで、通常のゲームでは絶対に見ることのできない隠しシナリオへと進むことができるのです。
縦読みの暗号は、プレイヤーの探究心を刺激するとともに、ゲーム画面の外側にある「リセットボタン」という物理的なオブジェクトを操作させることで、現実とゲームの境界線を曖昧にする試みでした。
「ここで理せっとしろ」の正確な意味
#知らない人には意味不明なゲーム内の言葉
ここで理せっとしろ(縦読み)スーパーファミコン版 #かまいたちの夜 #チュンソフ党の陰謀 #レトロゲーム pic.twitter.com/xllbsm83hL
— X0@もりそば (@X0_BR) November 17, 2023
スーパーファミコン版で縦読みされる「ここで理せっとしろ」というメッセージは、一見すると「ここでリセットしろ」と読めるように見えますが、実際には「ここで理せっとしろ」と表記されています。「りせっと」ではなく「理せっと」というひらがなと漢字の混合表記になっているのです。
この不自然な表記は、暗号編のシナリオが「縦読み」という謎解きを含む内容だったことと関連していると考えられます。プレイヤーにゲーム機本体のリセットボタンを押させるという物理的な行動を促す指示だったのです。
ゲーム内のキャラクターがプレイヤー自身に語りかけるという「第四の壁」を破る演出は、当時としては非常に斬新なアプローチでした。多くのプレイヤーにとって、このメッセージを見つけ、実際にリセットボタンを押す勇気を持つこと自体が一種のゲーム内挑戦だったと言えるでしょう。
「ここでリセットしろ」は単なるゲームオーバーメッセージではなく、物理的なリセットボタンを押すよう促す開発者からの直接指示です。縦読みという仕掛けに隠されたこのメッセージは、ゲームと現実の境界を曖昧にする演出でした。
リセットボタンを押すとどうなるのか
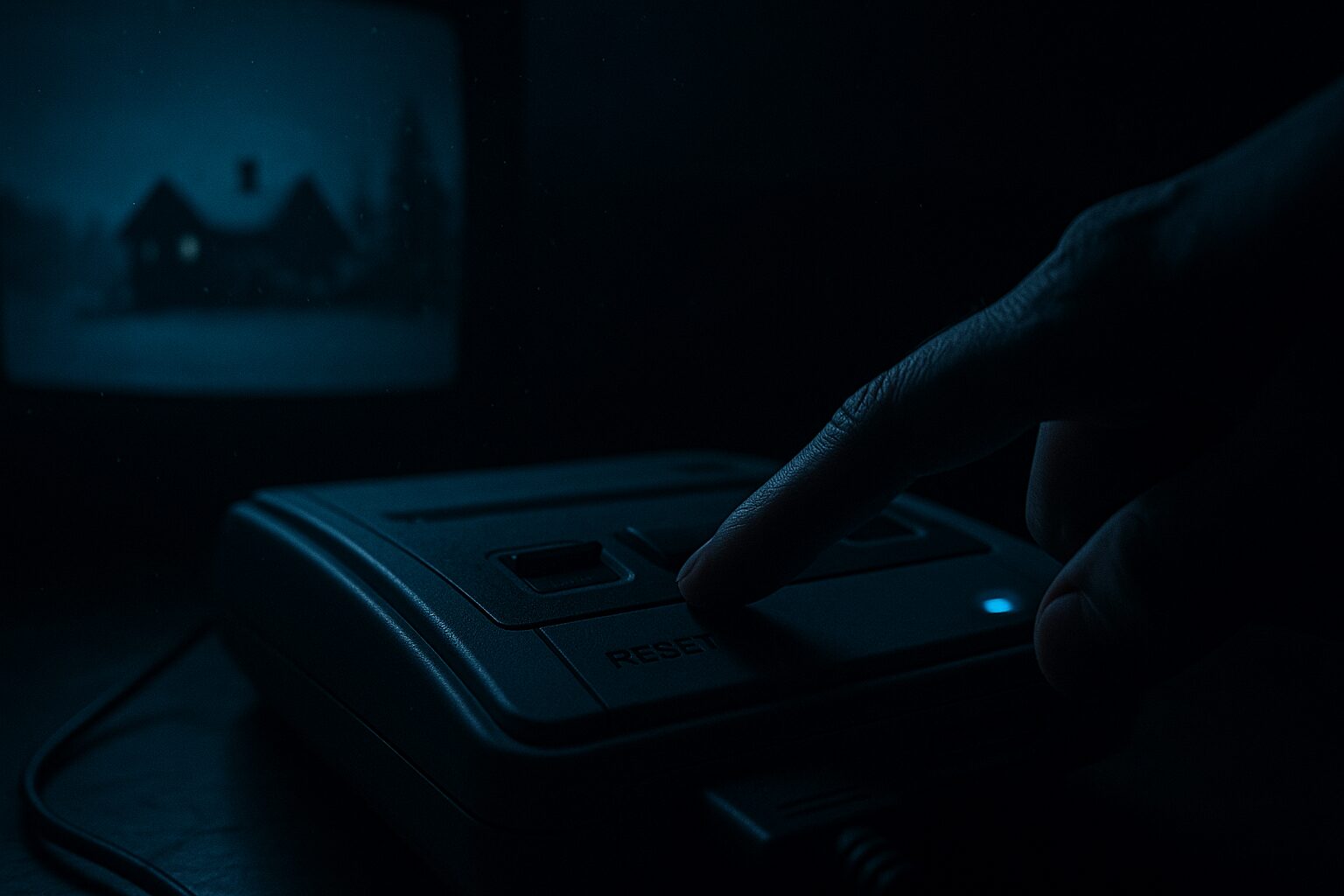
nerdnooks・イメージ
暗号編の宝探しシーンで縦読みメッセージを発見し、勇気を出してリセットボタンを押したプレイヤーを待っていたのは、ゲームの雰囲気を一変させる衝撃的な展開でした。通常、スーパーファミコンのリセットボタンを押すと、ゲームが再起動してしまうため、多くのプレイヤーはこの指示に従うことに躊躇したと言われています。
しかし、実際にリセットボタンを押すと、画面は真っ黒になり、BGMも停止します。そして、白い文字で「わたしの名前は我孫子武丸。いや、そういう名前で知られている人物の陰にいる、本当の作者。それがわたしだ。」という不気味なメッセージが表示されるのです。
この演出の特徴は、通常ではリセット操作によってゲームが初期化されるところ、ソフト側でリセットイベントを検知して特別な演出を表示するという工夫がなされていた点です。技術的には、ソフトリセット時のRAM状態を利用した演出だった可能性が考えられます。
開発関係者のインタビューによれば、この仕掛けは我孫子武丸氏がシナリオライターとして「選択肢以外の行動をさせたい」という意図を持ち、それに対して麻野一哉氏らがリセットボタンを使った案を提案、その上で我孫子氏がシナリオを書いたという計画的な流れがあったことが語られています。
チュンソフ党の陰謀編への入口
チュンソフ党の陰謀編怖かったよね。
こっそり窓の外を確認した純情ボーイ時代— 🎲DICE🗻🇦🇶 (@Dice_Cubelic) October 9, 2018
リセットボタンを押した後に表示される隠しメッセージは、通称「チュンソフ党の陰謀編」と呼ばれています。このシナリオでは、シナリオライターの我孫子武丸氏がプレイヤーに直接語りかけるという体裁のメタフィクション的な内容になっています。
「我孫子」を名乗る人物は、ゲーム会社チュンソフトに監禁され、シナリオを強制的に書かされていると告白します。さらに、チュンソフトの真の目的はゲームを通じて子供たちを洗脳することであり、いずれ「チュンソフ党」という巨大組織となって日本を支配するだろうと警告するのです。
メッセージの内容は、国民がチュンソフ党製のインスタント食品を食べながら、廃人のようにゲームをプレイし続けるディストピアの到来を予言し、「彼らの足音が聞こえる」という緊迫した言葉で締めくくられます。
このブラックユーモアと企業風刺、そして背筋が凍るような不安感を融合させたメタフィクションは、ゲームという娯楽が持つ中毒性や企業構造を風刺したものと解釈できます。発表から数十年経った今でも色褪せない鋭い批評性を持っているのです。
チュンソフ党の陰謀編は、単なる怖い話ではなく、ゲーム業界や企業社会に対する風刺が込められた作品内作品と言えます。このメタフィクションによって、プレイヤーはゲームキャラクターとしてだけでなく、現実の消費者としての自分自身を客観視するよう促されるのです。
移植版での違い(セレクトボタン等)

nerdnooks・イメージ
「かまいたちの夜」は様々なプラットフォームに移植されましたが、移植の際に「ここでリセットしろ」の仕掛けにも変更が加えられています。各機種での違いを見ていきましょう。
| プラットフォーム | 縦読みメッセージ | 実行する操作 |
|---|---|---|
| スーパーファミコン | ここで理せっとしろ | 本体のリセットボタンを押す |
| PlayStation | せれくとをおせ | コントローラーのSELECTボタンを押す ※本体にもリセットボタンは存在するが使用しない |
| ゲームボーイアドバンス | せれくとをおせ | コントローラーのSELECTボタンを押す |
| 携帯アプリ/スマートフォン | 機種により異なる | 特定画面のタップなど |
特にPlayStation版では、本体にリセットボタンが存在するにも関わらず、操作方法がコントローラーのSELECTボタンに変更され、縦読みも「せれくとをおせ」と変わっています。これは移植上の仕様変更として行われたものです。
「輪廻彩声」というPlayStation Vita/Windows版では、縦読みは「ここにもどれ」となっており、このメッセージが表示されているときにバックログ画面で該当行に△ボタンでジャンプすると陰謀編に突入するという、より複雑な仕掛けになっています。
ただし、いずれの移植版でも「隠された命令を発見し、通常とは異なる操作を行う」という核心的な体験は継承されています。ハードの特性や制約を踏まえつつ、オリジナル版の驚きと発見を再現しようとする開発者の工夫が感じられます。
かまいたちの夜におけるリセットしろの指示から生まれた都市伝説

nerdnooks・イメージ
- 謎の電話番号は実在するのか
- 開発者たちによる意図的な仕掛け
- 当時のプレイヤーに与えた衝撃
- メタフィクションとしての意義
- サウンドノベルの先駆的ギミック
謎の電話番号は実在するのか
「かまいたちの夜」の隠しメッセージと関連して、「特定の電話番号が表示される」という噂が広まりました。しかし、結論から言うと、この噂は完全な都市伝説です。ゲーム内に開発者が意図的に埋め込んだ電話番号は存在しません。
では、なぜこのような噂が生まれたのでしょうか。これには複数の要因が考えられます。まず、ゲーム内に存在する本物の隠しメッセージ(リセット指示)がプレイヤーの好奇心を刺激し、他にも秘密があるのではないかという期待を生み出しました。
さらに、日本には古くから「かけてはいけない電話番号」という都市伝説が存在します。このような既存の都市伝説のテンプレートと、謎に満ちた「かまいたちの夜」の秘密が結びつき、新たな噂として広まっていったと考えられるのです。
当時はインターネットが一般に普及する前の時代で、情報の検証が難しかったことも、この噂が広まる要因となりました。友人から友人へと口伝えに伝わる中で、事実とフィクションの境界が曖昧になり、「電話番号が表示される」という噂が一人歩きしたのです。
「かまいたちの夜」に隠された電話番号は存在しません。この噂は、実在する「ここでリセットしろ」の隠しメッセージと、日本の「かけてはいけない電話番号」という都市伝説が混ざり合って生まれたものです。信頼できる資料や開発者の証言にも、電話番号の存在を裏付ける証拠はありません。
開発者たちによる意図的な仕掛け
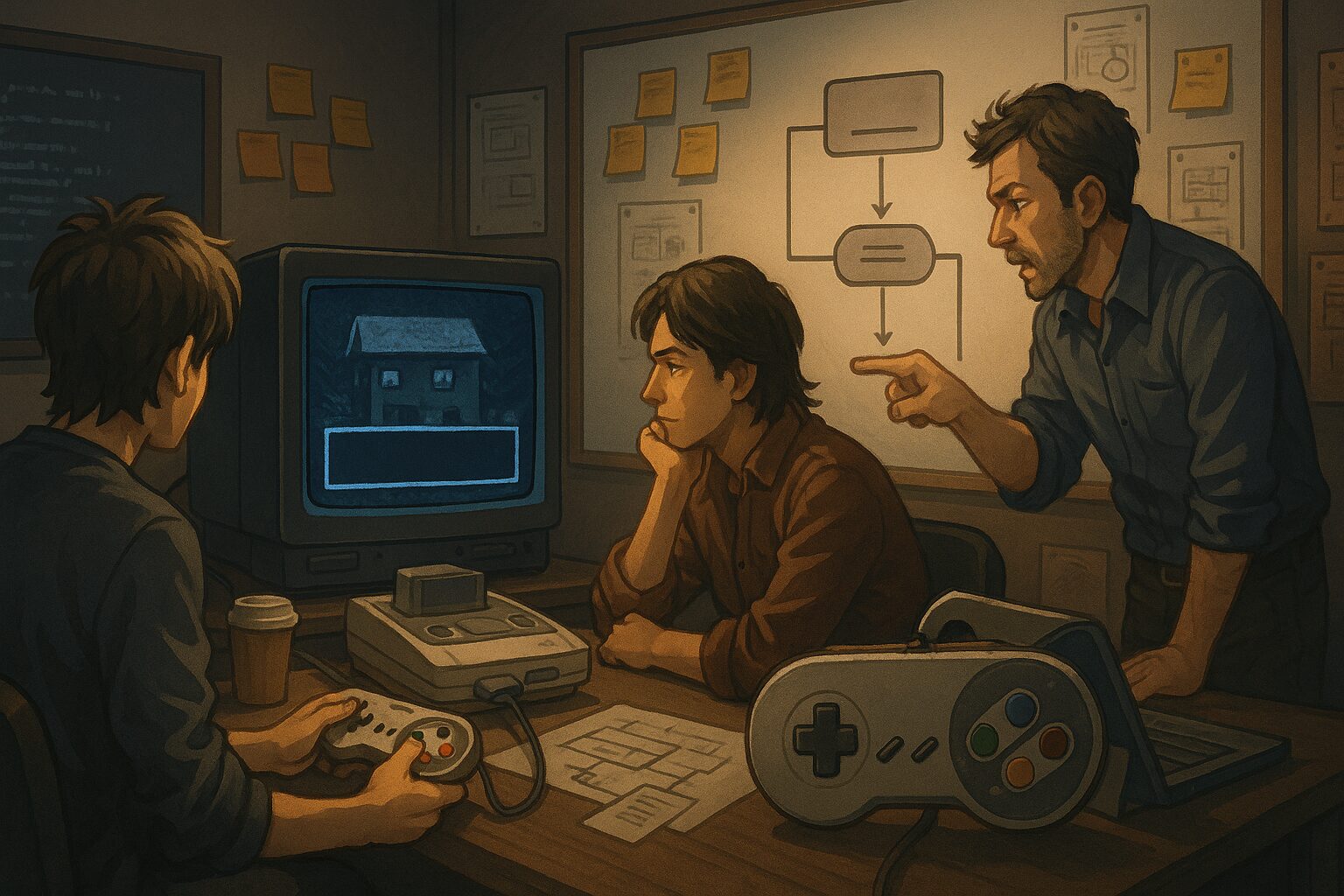
nerdnooks・イメージ
「ここでリセットしろ」の仕掛けは、開発チームによる意図的な設計でした。4Gamerの30周年記念インタビューなどによれば、この革新的なアイデアが生まれた経緯について詳しく語られています。
シナリオを担当した我孫子武丸氏は、「総当たり」だけでゲームを解けないようにするため、プレイヤーに選択肢を選ぶ以外の行動をさせたいと考えていました。その一つの答えがミステリー編の犯人名入力でしたが、それ以外にも特殊な状況で使える仕掛けはないかとチュンソフトに相談したのです。
これに対し、ディレクターの麻野一哉氏からリセットボタンを使った仕掛けが提案されました。「リセットボタンと聞いたら、ゲームの内容を文字通り全部リセットして、プログラムが1からやり直しになると思いますよね。でもスーパーファミコンのリセットボタンはそうじゃない」と麻野氏は説明しています。
我孫子氏はこのアイデアを聞いて「じゃあ、それ用のシナリオを書きます」と応じたといいます。実は彼は、アメリカの推理/SF作家フレドリック・ブラウンの「うしろを見るな」という短編を下敷きに、チュンソフ党の陰謀編のシナリオを構想していたのです。
このように、技術的な可能性とクリエイティブなアイデアが融合することで、ゲーム史に残る伝説的な隠しメッセージが誕生しました。それは単なるイースターエッグを超えて、メディアとプレイヤーの関係性を問い直す試みでもあったのです。
当時のプレイヤーに与えた衝撃
アドバンスかまいたちの夜進めてる やっぱりチュンソフ党の陰謀編は面白いな 当時メッチャ興奮した
— タカト (@tktkck) October 10, 2021
1994年に発売された「かまいたちの夜」の「ここでリセットしろ」の仕掛けは、当時のプレイヤーに強い印象を与えました。この衝撃の大きさを理解するには、当時のゲーム環境を考慮する必要があります。
当時のプレイヤーにとって「リセットボタン」は、ゲームを再起動するためのものであり、プレイ中にむやみに押すと、セーブデータが失われたり進行状況が台無しになったりする危険なボタンでした。そのため、ゲーム内のメッセージに従ってリセットボタンを押すという行為には、大きな心理的ハードルがあったのです。
また、インターネットが普及していない時代では、ゲームの攻略情報は雑誌や友人との情報交換に限られていました。「かまいたちの夜」の隠しメッセージはあまりにも見つけにくく、実際にリセットボタンを押す勇気を持ったプレイヤーも少なかったため、この秘密を知る人は非常に限られていました。
偶然この仕掛けを発見したプレイヤーにとっては、ゲームキャラクターではなく開発者自身がプレイヤーに直接語りかけてくるという体験は、現実とフィクションの境界を曖昧にする不気味さとともに、特別な「秘密を共有している」という感覚をもたらしました。
当時の攻略本にも詳しく載っていなかったこの仕掛けを知った友人は、「本当にリセットボタンを押すと、ゲーム会社の陰謀が明かされるんだ」と語ってくれました。実際に試してみると本当にあの不気味なメッセージが表示されて、当時のゲームでここまでメタな演出をしたのは画期的だと感じました。
メタフィクションとしての意義

nerdnooks・イメージ
「ここでリセットしろ」と「チュンソフ党の陰謀編」は、単なる隠し要素を超えて、メタフィクションとしての意義を持っています。メタフィクションとは、フィクション作品がその虚構性を自ら暴露し、作品世界と現実世界の境界を曖昧にする手法です。
「かまいたちの夜」のこの仕掛けは、ゲーム内のキャラクターではなく、シナリオライター自身がプレイヤーに直接語りかけることで、ゲーム世界の外側にある現実を意識させています。さらに、ゲームを製作した会社自体を「悪の組織」として描くという自己言及的な風刺を行うことで、プレイヤーに「これはゲームなのか、それとも何かの真実なのか」という混乱を生じさせます。
最も特徴的なのは、プレイヤーに物理的なリセットボタンを押させるという行為を通じて、ゲームという媒体の枠組みそのものを問い直している点です。通常、ゲームプレイとは画面内の出来事に対してコントローラーで反応することですが、この仕掛けはその常識を覆し、ゲーム機本体への物理的な働きかけを要求します。
この革新的なアプローチは、後のゲーム開発者たちに影響を与え、「メタルギアソリッド」シリーズなどのゲームにおいても、ゲームの枠組みを超えた演出が取り入れられるようになりました。「かまいたちの夜」は、ゲームという媒体の可能性を広げた先駆的な作品だったのです。
サウンドノベルの先駆的ギミック
「ここでリセットしろ」の仕掛けは、サウンドノベルというジャンルの特性を活かした要素です。チュンソフトが確立したサウンドノベルは、「音のついた小説をテレビ画面を通して楽しむことができるソフト」と定義されていました。この新しいジャンルは、従来のゲームの枠を超えた体験を提供するものでした。
サウンドノベルの先駆作である「弟切草」に続く第2弾として発売された「かまいたちの夜」は、さらに大胆な試みとして「ここでリセットしろ」のギミックを導入しました。これはサウンドノベルの本質である「読み手の想像力を最大限に引き出す」という理念を具現化したものでした。
このギミックが特に画期的だったのは、「プレイヤーの行動」をゲームの要素として取り込んだ点です。通常のゲームではキャラクターの行動を操作しますが、「ここでリセットしろ」ではプレイヤー自身の物理的な行動がゲーム進行の鍵となります。
また、この手法は続編の「かまいたちの夜2 監獄島のわらべ唄」にも発展的に継承されています。「2」では「洞窟探検篇」において、特定のコマンド/ボタン入力で隠しメッセージが表示されるという、方法は異なるものの同様のメタ的演出が取り入れられているのです。
サウンドノベルというジャンルは、プレイヤーの想像力を刺激し、テキストと音と映像が一体となった独自の物語体験を提供しました。「ここでリセットしろ」のギミックは、その理念を突き詰めた先にある、メディアの枠組みを超えた実験的な試みだったと言えるでしょう。
総括:かまいたちの夜「ここでリセットしろ」の謎と仕組みを解説
- 「ここでリセットしろ」は暗号編の宝探しシーンで縦読みにより発見できる隠しメッセージ
- スーパーファミコン版では「ここで理せっとしろ」と表示され、本体のリセットボタンを押すよう促している
- リセットボタンを押すと「チュンソフ党の陰謀編」という隠しシナリオが表示される
- 陰謀編では我孫子武丸を名乗る人物がチュンソフトの秘密を暴露するという内容
- 移植版では「せれくとをおせ」(PlayStation/GBA)や「ここにもどれ」(Vita/Windows)など、ハードに合わせた指示に変更されている
- 噂されている「謎の電話番号」は実在せず、完全な都市伝説である
- この仕掛けはシナリオライターの我孫子武丸氏とディレクターの麻野一哉氏の共同発案による計画的な設計
- インターネット普及前の時代には、この秘密を知る人は非常に限られていた
- ゲームの枠を超えたメタフィクション的な演出として評価されている
- プレイヤーに物理的な操作を要求するという革新的なアプローチ
- 「かまいたちの夜2」では「洞窟探検篇」のコマンド入力など、発展的に継承されている
- プレイヤーのコミュニティ形成にも貢献した共有体験として記憶されている
- サウンドノベルという新ジャンルの可能性を広げた試み
- 発売から30年近く経った現在でも語り継がれる伝説的な隠し要素
- 「第四の壁」を破る演出として、後のゲーム開発に影響を与えた